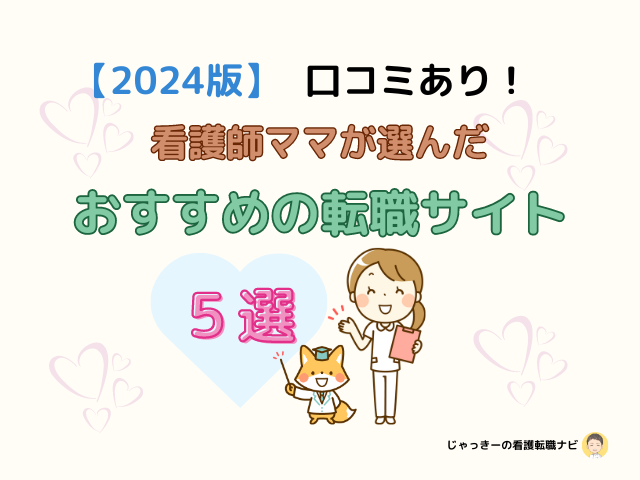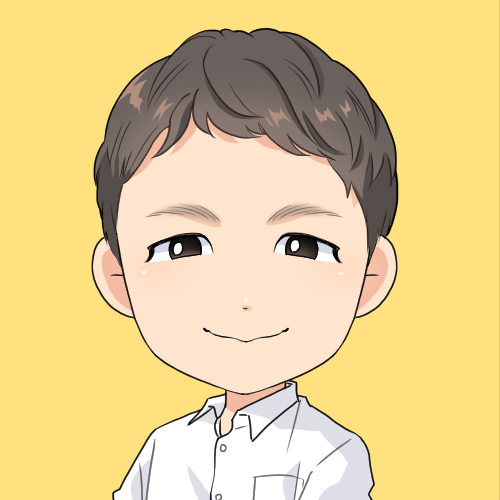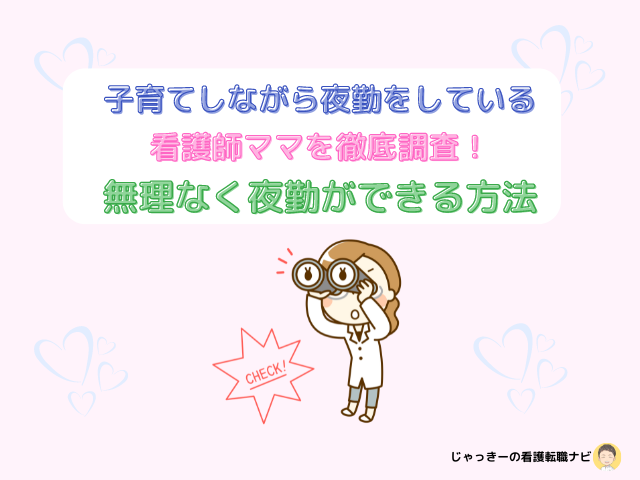
- 将来の教育費や生活資金をもっと貯めたいけど、夜勤ができるか不安です。
- 子どもが小さい今の状況でどうやって夜勤ができるわけ?誰か教えて〜。
「未就学児の小さな子どもがいても夜勤ができるの?」
と、悩んでしまいますよね。
本記事では、小さな子どもを育てながら、無理なく夜勤ができる方法を紹介します。
本記事を読めば、自分と子どもの心身が健やかなまま、看護師の夜勤ができます。
「夜勤に入って少しでもお金を稼ぎたいけど、子どもが小さい時にどうしたら夜勤ができるの?」
と不安や悩みを持っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
子育てしやすい病院探しは、ナース人材バンク
ナース人材バンクは、常勤(フルタイム)で仕事を探している方にオススメです!
「2023~2024年 オリコン顧客満足度®調査」で、2年連続の総合第1位を獲得。
※調査対象:過去7年以内に人材紹介会社を利用して転職したことがある20~69歳の看護師896人

転職実績で選ぶなら、ナース人材バンクは外せません。
日本最大級!年間利用者数10万人以上
簡単1分で登録完了!転職サポートは全て無料
最優先!看護師が子育てしながら夜勤が続けられる2つのポイント

子育てしながら夜勤ができるには、次の2つのポイントで協力が得られるなら、成功率はグンっと上がるでしょう。
<2つのポイント>
祖父母の協力が得られる
夜勤をする看護師ママにとって、祖父母は子どもを預かってもらえる、とても助かる存在です。
夜勤をするにあたり、祖父母が近くに住んでいて、子どもを見てくれる環境があるのはとても心強いです。
しかも、「自分の親」というところもポイント。

旦那さんの両親だと気をつかっちゃいますもんね。
小さな子どもがいて夜勤を続けるには、祖父母の協力は必須といって良いでしょう。
パートナーの協力がある
当院の看護師ママのAさんは、小学生2人のお子さんをもつ元気で明るい方です。
毎週土曜日に夜勤をしています。
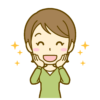
ウチの旦那さんは土日が休みなんですよ〜。
だから、土曜日の夜は旦那さんにね、ちゃんと子育てを協力してもらってます。
と話していました。
また祖父母の協力が得られるBさんも、両親に毎回迷惑はかけられないとのことで、

夜勤のときは、旦那の休みを調整してもらってます。
と言っていました。
自分の家庭のことですから、やっぱり

「パートナーの理解」と「一緒になって実行してくれる行動力」が不可欠。
パートナーである、旦那さんが2人3脚で歩いてくれることで、夜勤が続けられます。
環境を改善!看護師が子育てしながら夜勤ができる3つのポイント
看護師が子育てしながら夜勤をするには、最優先のポイントのほかに、夜勤がしやすい環境も重要です。
病棟が子育てに理解ある対応をしてくれる
夜勤をする上で、勤務日を調整してくれるという病棟の柔軟な対応もポイントです。
特に、勤務スケジュールを管理する
- 病棟師長の子育てに対する考え方
- 病棟師長との関係性
が重要になってきます。
日々のコミュニケーションをとりながら、自分の状況を伝えておきましょう。
私が働く小規模な病院では、スタッフの意見に耳を傾け、できるだけ希望にそった勤務に配慮してくれる師長さんが多いです。

私も、特に子育て中の看護師には、希望のシフトになるよう、
柔軟な対応を心がけています。
大規模な病院やスタッフの多い職場では、そういう訳にもいかないかもしれませんよね。
当院のような小規模病院であれば、
- 夜勤の希望の有無
- 希望の曜日や回数
なども相談できます。
このように、まずは子育てに理解がある病院や職場を選ぶことが重要です。
病院に24時間対応の託児所がある
24時間対応の託児所付きの病院があれば、夜勤中に預けることができるので安心です。
しかも、病院の敷地内にあるので、何かあってもすぐに駆けつけられる良さがあります。
看護師ママの意見としては、
「勤務中だけじゃなく勤務時間外でも預けられるサービスがあれば、出勤前後の仮眠ができるのにな〜。」
という希望がありました。

時間外サポートがあれば、看護師ママもホッとひと息つけるのに!
と本気で思いますね。
子育て中の看護師ママが多い
子育て中の看護師ママが、たくさん勤務しているのも、1つのポイントです。
なぜなら、同じような境遇の人たちが夜勤を行えているのなら、自分にもできる可能性が高いからです。
また、子育て中だと共通する話題も多く、コミュニケーションも取りやすくて、仕事もやりやすくなります。
さらに、ホットな子育て情報が共有できる、育児や家庭のグチも分かち合える、といったメリットも大きいです。

ママさんが多い職場だと、お互いさま精神があるので気持ち的にも楽というママが多いです。
夜勤がしやすい環境か?職場の見直しはできる!

祖父母やパートナーの協力がむずかしい場合であっても、職場の環境を見直して、夜勤に臨むことだって可能です。

今の職場はどうでしょうか?
子育て中の看護師ママに優しい対応をとってくれますか?
実際に、夜勤をしている先輩や同僚の看護師ママがいますか?
もし周りに、お手本となるような働き方をしている看護師ママを見かけないのなら、
夜勤がしやすい病院へ転職するのも1つの方法です。
は、病院や施設に知り合いでもいない限り、職場の中を伺い知ることはむずかしいです。

しかし、そんな時に頼りになるのが、看護師専門の転職サイトです。
病院の内情を知るアドバイザーから、病院の中の様子をつぶさに聞いてしっかりと情報収集をしましょう。
夜勤が続けられる病院への転職成功のカギは「事前にどれだけ情報を手に入れられるか」です。
病院に託児所があるかや、職場の雰囲気、看護部長や師長さんの子育て感、看護師ママの夜勤状況などを、アドバイザーさんから聞いておきましょう!
子育て中の夜勤に向かないポイントも押さえよう
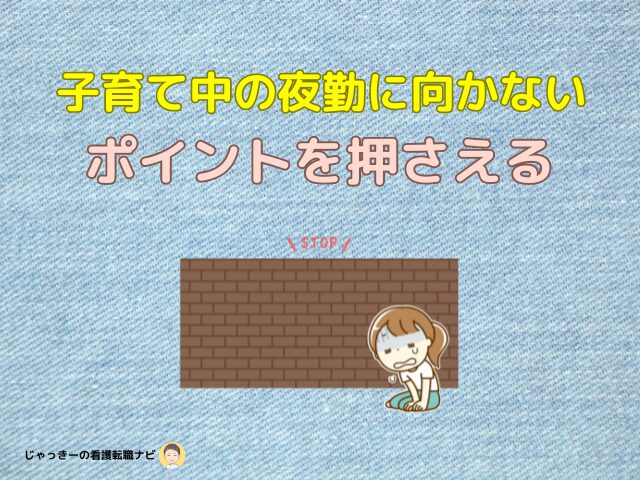
反対に、子育て中の夜勤には向かないポイントも押さえておきましょう。

ほとんどが、夜勤ができるポイントの逆だと思ってもらえれば分かりやすいです。
<子育て中の夜勤に向かないポイント>
- 祖父母の協力が得られない
- パートナーの協力が得られない
- 子育てに理解がない職場
- 病院に24時間対応の託児所がない
- 子育てしながらの夜勤は子どもに悪影響だと周囲の反対がある
- 子どもが小さい内は子どもとの時間を大切にしたい
自分の状況と照らし合わせて、ポイントに多く当てまるようであれば、夜勤に不向きな状況かもしれません。

少し自分の状況を見直す時間をもうけましょう。
子育てしながらの夜勤は想像以上に心と体が疲れる
蚊帳の外から見ると、
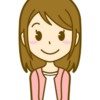
意外と子育てしながら夜勤もできそうかも?
と思ってしまいがちです。
しかし、実際に夜勤をするのと、遠目から見ているだけとは大違い。
すんなりと夜勤をこなしているあの人も、実はいくつかのハードルを越えて夜勤をしています。
家事・育児をしながら、さらに看護師の夜勤をこなす。
これが、どれほどすごいことか。
尊敬しかありません。

子育てしながらの夜勤で、自分を大切にするためにも、
子育てしながら夜勤ができる環境をしっかりと整えて臨みましょう。
子どもが小さい時の働き方は夜勤を避けても良い
子どもが小さい時の働き方に、夜勤をオススメするかは、家庭の状況によって異なります。
もちろん、夜勤ありフルタイムで仕事をするのもOKです。
しかし、準備を怠って安易に夜勤をすると、「子育てしながら看護師の夜勤はムリ!」と失敗してしまいます。
そもそも、
- 子どもや家族との時間をより大切にしたい
- 夜勤をするにはサポートが少ない
- 子どもが小さい内は夜勤をしたくない
という方は、ムリをせず時短制度を活用した「日勤常勤や、日勤パート」がオススメです。
子どもが成長すれば、また夜勤にチャレンジできる機会が必ず訪れます。
子どもが小さい頃は「どの働き方が正解」というものはありません。

「子育てや仕事にどう向き合うか」といった自分の軸を決め、
決して無理をしない働き方を心がけましょう。
【注意】看護師の職場では物理的に子育てしにくい環境もある
看護師の職場では一部、もともと子育てしにくい環境があります。

子育てしにくい環境とは、大学病院や総合病院、急性期病棟での仕事です。
たくさんの看護師ママが、子育てのしにくさを口にしています。
特に大学病院や総合病院は最先端の医療・看護を提供しています。
故に、自ら進んで学ぶ努力と行動が要求されます。
- 高度な医療の提供
- 現場での新しい看護の実践
- 業務終了後や休日の勉強会・研修への参加
- 看護研究と学会発表
- 残業も多くなる
があって、看護師ママに風当たりが強くなっている子育てしにくい環境です。
職員の年齢階層が、卒後すぐの若手看護師とベテラン看護師で構成される。
20代後半〜40代の子育て中の看護師がごっそりいないのが、風当たりの強さと、子育てのしにくさを物語っています。
| 職場 | 歓迎する年代 | 特徴 |
| 急性期病院 | 20代~30代 | 長時間労働や夜勤も多いため、体力があり業務スピードにも対応できる若い世代が多い。 |
| 大学病院 | 20代後半~30代 | 大学病院での退職者が多い層(20代後半〜30代)の人手が不足する傾向にある。 |
大学病院や総合病院では、救急搬送や重症患者、手術件数も多いです。
忙しい職場であれば、子育て中の看護師ママでは勤めきれない可能性があります。
ただ、あまり悪く捉えてほしくないのです。
大学病院などの医療機関は、看護師ママへ、わざと風当たりを強くしているのではありません。
その求められる責務から風当たりが強くなってしまう環境なのです。
あなた3年目だったわね。今年から業務リーダーをお願い。あとプリセプターもお願いね。それに院内の委員会にも出て欲しいわ。係活動も忘れないでね。あ、そろそろ看護研究を始める年代ね。出て欲しい外部研修もあるの。
— カメさん@男性看護師 (@49_kame) July 22, 2023
ちなみにどれも自己研鑽だから手当は無いわ。全部あなたのためよ。よろしくね。 pic.twitter.com/W3guz8nmNi
大学病院や総合病院ではこんな光景が日常にありますよね。
看護師で夜勤をしながら子育てしやすい職場環境
しかし、反対に、
- 療養型施設
- リハビリテーション病院
- 介護老人保健施設
- 療養病棟
- 精神科病棟など
といった、

看護師で夜勤をしながらも、子育てしやすい職場があるのも事実です。
救急搬送や重症患者は少なく、手術を扱っている病院はほとんどありません。
定時帰りがスタンダードで、子育てと仕事の両立がしやすく、看護師ママの割合が必然的に多くなるからです。
もし今の職場で働きにくさを感じているのなら、転職も視野に入れて転職のプロに相談するのも1つの方法です。
大学病院や総合病院に比べて、夜勤業務の負担も少なく、働きやすい職場は必ずあります。

当院のような、精神科病棟・療養病棟だけの病院などは、看護師ママが夜勤をするには、うってつけです!
<子育てしやすい職場探しを転職のプロへ相談>
日本最大級!年間利用者数10万人以上
簡単1分で登録完了!転職サポートは全て無料
子育てしながら夜勤をする時の注意点

子育てしながら夜勤をする場合、以下2点に注意しておきましょう。
子どもへの影響
子どもが小さい頃に夜勤をする場合、子どもへの影響がでる可能性があることを認識しておきましょう。
- 機嫌が悪くなる
- ママがいなくて寂しいと甘えがひどくなる
- 悲しい表情が増える
- 保育園に行きたがらない(準備に時間がかかる)
- 大泣きすることが多くなる
- 寂しさから不眠になる
といった影響を耳にします。

まだまだ幼い子どもです。
夜にママが側にいない寂しさが募るときもありますもんね。
パートナーや祖父母、保育園や託児所などと連携して、
できる限り子どもの気持ちに寄り添いながら、みんなでフォローしていきましょう。
ひとりで頑張りすぎず、みんなで育てるを心がけてくださいね。
子どもへ影響が出たときの対処法

もし万が一、子どもへ悪い影響が出たら、
いったん夜勤を中止して、子どもとしっかり向き合う時間を作りましょう。
ママが子どもの側にいて、接して見守る時間が増えると、子どもは安心し症状の軽減・消失につながります。
状況が改善したら、家族と相談してまた夜勤をスタートすればOKです。
自分の体調管理
子育てしながら夜勤をする際、自分の体調管理は非常に重要です。
自分が体調を崩すと、子どもの世話や家事には支障がでるし、夜勤シフトの交代が発生するなど、影響が大きいです。
「職場に迷惑をかけてしまった。」と自己嫌悪に陥りがちになります。

周囲のサポートをうまく受けながら、自分を守ってあげましょう。
フルタイム(夜勤)が続けられる看護師ママの体験談

小さな子どもを子育てしながら、夜勤をしている看護師ママたちの体験談を聴いてみましょう。
子育てしながら夜勤をする看護師ママの体験談

夫婦ともに夜勤のある生活をしています。
子どもは2人いて、下の子の時が生後8ヶ月で仕事復帰。
1歳の頃から夜勤を再開しました。
下の子は今現在4歳です。
私の勤める病院の託児所は、平日日中のみのあずかり。
なので、子どもは保育園にあずけています。
ちなみに私は2交替です。
夫の夜勤とは重ならないようにシフトを調整。
私が夜勤の日は、朝から保育園へあずけます。
仕事を終えた夫が迎えに行って、ご飯やお風呂も全部やってくれています。
翌日は、夫が保育園へ連れて行き、明けの私はゆっくり休んで夕方お迎えに行きます。
参考:Yahoo!知恵袋
総合病院勤務です。
上司から、続けるなら「ばぁば(祖母)」に預かって貰わないと無理だよ。
と言われましたね…
時短でも大体の人は、同居かなという印象です。
元々残業の多い職場。
「残業なし」という約束でしたが、そんな訳にもいかず。
保育園のお迎えも、近所のばぁば任せになってしまいました…
せめて「近い場所に転職したいなぁ」と考えています。
参考:Yahoo!知恵袋

夜勤をする看護師ママの体験談(番外編)

2歳の子どもがいます。療養病棟に異動・復帰し1年が経ちました。
うちの師長は、
「今は子どもが小さくても働ける形で働けばいい。その分また働けるようになったらガッツリ働いてね。」
と言ってくれます。
育児中は育児・家事だけでも大変です。
仕事も、いい気分転換になるくらいが、ちょうどいいのではないかと思います。
勤務場所は、外来に行っても病棟に行っても、どこでも大差ないような気がします。
理解のある職場、それが一番ですよ。
私はつくづくそう思いました。
参考:Yahoo!知恵袋
子どもが小さいときは、うんと子どもの側にいてあげたい。
たくさんのママが思うことです。
子育ての時間は、本当に一瞬です。
長いように見えて、振り返ればいつの間にか大人に近づいている。

夜勤のある日は、夫や祖父母に思い切って任せる。
そのぶん、お休みの日は、たっぷり側にいてあげましょう!
<子育てしやすい職場探しはナース人材バンク>
日本最大級!年間利用者数10万人以上
簡単1分で登録完了!転職サポートは全て無料
まとめ「子育てしながら夜勤をしている看護師ママを徹底調査!無理なく夜勤ができる方法」
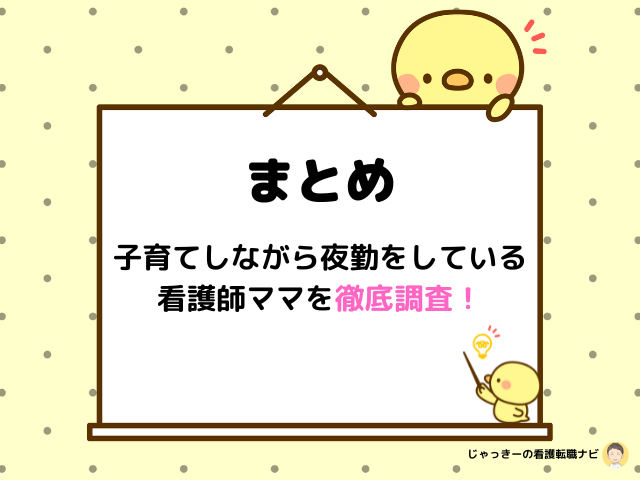
子育て中の家庭には、教育費、生活費、遊興費といった、たくさんのお金がどうしても必要になってきます。
「夜勤ができればもっと生活が楽になる」なんて声もしばしば。
しかし、子育て中に夜勤をしたいけど、できるかどうか不安で悩んだまま、一歩踏み出せずにいる方も非常に多いです。
そこで今回、小さな子どもを育てながら、無理なく夜勤ができる方法を紹介しました。
子育てしながら夜勤ができるポイントをしっかり押さえることで、自分と子どもの心身が健やかなまま、看護師の夜勤ができるでしょう。
「夜勤がしたい!でも子育て中は夜勤なんてできるの?どうしたらいいの?」
と、お悩みの方は、ぜひ本記事の内容を参考にしていただけたらと思います。

少しでも、みなさんのお役に立てれば幸いです。
ではまた。
日本最大級!年間利用者数10万人以上
簡単1分で登録完了!転職サポートは全て無料
あわせて読みたい記事はこちら!